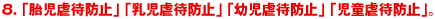 |
| |
「児童虐待」について現時点では「虐待ホットライン」や「児童虐待防止法」など0歳〜18歳までを対象とした行政の具体的施策が見られます。そして「虐待発見件数」などは数年前より大きく数字を伸ばしている地方自治体もあり、地域密着型の取り組みにて活動をされている組織・団体による功績も良い結果をもたらしているという報告も多く聞きます。ただ、あくまでも虐待が起こってからの施策という位置付けであり、問題は虐待を起こしそうな家庭を事前に発見できていない点が上げられています。
ならば、もっと前段階での取り組みが必要となります。これはまさに「虐待を防止」するということに他なりません。
専門書によると3日に一人の割合で赤ちゃんが死んでいます。泣きやまないがためについ行ってしまう「揺さぶり症候群」による事故や、母親が2時間おきに母乳をあげていた赤ちゃんが泣きやまず、父親が死亡させてしまった事件の真相が、「母親の母乳が出ていなかった」などは、知識不足から見られる全く特殊ではない、乳児虐待の例なのです。新聞やTVなどに出る虐待のニュースは氷山の一角で、悲しいことに今もマンションの一室で多くの虐待が行われているのが実状なのです。
核家族化による子育て支援(お婆ちゃんの知恵袋)がなく、マンション生活で隣近所の交流もない…そんな時代における「密室での子育て」という、ストレスが募る生活環境では、つい「うまく行かない子育て」へと流れてしまいます。「乳・幼児虐待」は発見されにくい時期でもあるということから、現時点では防止策がほとんど具体的施策として大きく取り上げられていません。どうすればこの発見しにくい「乳・幼児虐待」を防止・撲滅できるのかを、真剣に見つめ直さねばならないのです。
「乳・幼児虐待」の要因はひとつではありません。 社会的要因であるストレス、トラウマや誤認識、知識不足など、解決が難しい問題も少なくありません。「できちゃった結婚」が全体の30%を超えており、慌ただしく結婚式を挙げ、慌ただしく出産を迎え、両親共に育児をする時期であるにも関わらず「親としての自覚が芽生えていない」など、社会現象的要因も含めると根はとても深いものとなっています。昔ながらの「町ぐるみ」で子育て支援…というようなことも今では多くを見かけることはできません。このような環境での育児は若いお母さんにとって、「おかしくならないお母さんの方がおかしい。」とまで言われるようになっています。育児ノイローゼや育児期のうつ病が氾濫するしている要因はここにもあるようです。
|
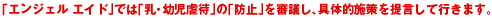 |
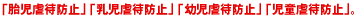 |
行政のデータによると、0歳〜18歳までを「児童」と定義しており、その中でも特に0歳〜1歳ぐらいを乳児、2歳ぐらい〜就学までを幼児と呼んでいます。つまり、行政が使用する「児童虐待」の言葉には、赤ちゃんも5歳児も高校生もひとくくりに対象者として含まれていることになります。・・・ここでちょっと疑問です。
高校生が受ける虐待と、赤ちゃんが受ける虐待を一緒に考えてもいいのでしょうか?何の抵抗もできない赤ちゃんと言葉で表現できる高校生に対する虐待は、加害者側の動機や背景も違ってくるでしょうし、防ぐための方法や事前のケアも全く違うと考えられます。そこでより具体的な話し合いができるように、当審議会ではひとくくりになっている「児童虐待」を4つに分けて考えることにします。
|
|
|